
恨人形心中語-うらみにんぎょうしんじゅうがたり-
|
近松は悩んでおりました。 竹本義太夫との約束の時期が近づいているというのに、脚本(ほん)がちっとも出来ないのです。 彼は人形浄瑠璃の作家でした。有名な脚本をいくつも書いて、その名と作品は広く知れ渡っております。けれどそんな近松にだって不調な時はあるのです。 彼はここのところ毎日のように、朝から晩まで、机の和紙に筆を入れては丸め、入れては丸めとそんな作業を繰り返しておりました。あれもだめ、これもだめ、座敷の畳の上には大量の紙くずが恨めしげに転がっています。あれやこれやと頭に案を浮かべるのですが、どの案もそれとは違うと頭の中で何かがささやくのです。彼は大衆の求める刺激を提供するのに優れておりましたから、そういった勘が働いたのでございましょう。しかし、大衆が何を求めているのか。その輪郭がはっきりとしないのです。困ったことに、脚本がなければ、人形の衣装を揃えてやることも稽古もできません。 彼は斬新な発想を必要としておりました。というのも、彼が属する竹本座のお膝元、黄金(こがね)の町に、円寿(えんじゅ)から宇治座がやってきて興行を始めたからでした。 依頼主の竹本義太夫も、作家の近松門左衛門も元は、宇治座の出身でありましたが、それぞれが野心を抱き独立し、手を組んだのでした。宇治座はそれがおもしろくありません。だから彼らの町にやってきて、それを潰そうと目論んだのです。そのような経緯で二つの座は興行合戦を繰り広げておりました。 当時の人形浄瑠璃といえばずいぶん昔の戦や武家のお家騒動を扱った歴史物や伝説・伝承を扱ったものでした。ですが、いつもの筋書き、いつもの脚本ではだめなのだと依頼主の義太夫も近松も感じておりました。彼らは新しい何かを求めていたのです。 「困ったのう。困ったのう」 門左衛門は嘆きました。歴史物は散々やってきましたし、宇治座とも被ります。そこに語りの違いはあっても目新しさはありません。 連日悩む様子の近松に妻が言いました。 「あなた、少し気分を変えたらどう。歌舞伎でも見てきたら如何」 それもそうだと思って、近松は芝居見物に出かけていきました。 このところ歌舞伎の流行は世話狂言でありました。密通や殺人事件など何かスキャンダラスな事件があると、歌舞伎役者達はすぐさまそれを演じて見せるのです。即興に近い形ですから演技の質は高くないのですが、人々は食いつき、芝居小屋は盛況でした。 この日見た演目は、江戸城大奥の女中と売れっ子歌舞伎役者が密通をし、それが大奥の面々と歌舞伎に関わる面々の双方に大勢の処罰者を出す大規模粛清事件に発展した、というものでした。 やはり出来は荒いのですが、人々は食い入るように見入っています。 ああ、今大衆が求めているものは遠い日の出来事ではなく、もっと近くで起こっている出来事なのかもしれない――近松は何かの取っ掛かりを得た気がいたしました。 歌舞伎を見終わった夕刻、帰ろうという頃に、困った事が起きました。黒い黒い雨雲が町全体を覆って、ざあざあばたばたと大粒の雨が降り出したのです。 近松は蕎麦屋に入って、やり過ごそうと致しましたが、蕎麦を食べ終わっても、酒を飲んでも一向に止む気配がありません。しかもそこそこ遠出をしてきたので、家まではずいぶん距離があります。仕方ない、どこかに宿を求めようと近松は考えました。 近くで見つけた宿はお世辞にも、よい宿とは言えませんでした。中はどんよりと暗いですし、なんだかじめじめとしていました。しかも玄関に飾られた黒髪の人形が、人形浄瑠璃作家から見ても何とも言えず不気味なのです。けれど雨宿りには代えられません。近松はさっさと布団に入ることに致しました。しかし、雨の音がうるさくてうるさくてなかなか寝付けませんでした。 そんな折、すすすっと部屋の襖が開き、何やら光が揺れました。 宿屋の主人か、それとも盗みか。近松は毛布から顔を出し襖の方向に目をやりました。そして、目を見開きました。 襖から部屋を覗いていたそれは人間ではありませんでした。身体は黒く、血のような赤い割けた目が輝いておりました。三本の角を持ち、口がぱっくりと裂けています。明らかに物(もの)の怪(け)の類でございました。その物の怪の背後で火の玉が二、三踊っております。 近松と目の合った物の怪はにいっと笑みを浮かべて言いました。 「人形浄瑠璃の近松門左衛門だな」 「そうだが」 近松は答えます。するとすぐさま物の怪は続けました。 「お前、浄瑠璃の題材を探しているのだろう? どうだ、ひとつ俺の話を取り入れてみないか」 瞬間、近松の目は作家の目に変わりました。ギラリと眼光が走りました。 「なにかあるのか」 布団から体を起こし、近松は物の怪に尋ねます。物の怪は再びにいっと笑いました。そうして、 「心中だ」 と言ったのでした。 すすすっとさらに襖が開きました。物の怪が長い腕を動かし手招きをすると男女の人形がふらふらと浮きながら入って参りました。物の怪は男女の人形を操りながら事の顛末を語りました。 「男は徳兵衛、女はお初という……」 物の怪は言いました。 広大な姥(うば)女(めの)森(もり)に分け入って、徳兵衛という男とお初という遊女が情死したのだと。二人は将来を誓い合っていたが、事情が生じたのだと語りました。 徳(とく)兵衛(べえ)は黄金の町で親方につき、商売をしていた。非常によい働きをしたので親方が自身の娘と結婚させようと考えた。そこで親方は徳兵衛の母のところに結納金を持っていった。だが、お初を想う徳兵衛はその話をあくまで固辞したのだった、と。 怒った親方は結納金を返せ、そして黄金の町から出て行けと要求した。徳兵衛は母から結納金を取り返す。親方に金を返して、あくまで自身の気持ちを貫こうとしたのだ。 そこに徳兵衛の友である九平次が現れた。どうしても金が要るという九平次に徳兵衛は三日限りの約束で結納金を貸してやった。だが約束の日、九平次は裏切った。証文があるにも関わらず「借金など知らぬ、証文も偽物だ」とのたまった上、公衆の面前で散々に痛めつけたのだ……。 「徳兵衛はすっかり面目を失ってしまった。親方に金を返すことも出来ぬ。とどめはお初に舞い込んだ身請け話よ。それでとうとう決意したのだ」 物の怪の赤い目が爛々と輝きました。そうしてかっと両腕を上げました。 「徳兵衛はお初と姥女森の奥に分け入り、共に死ぬことにした……」 見ると物の怪の前で男の人形が刀を振り上げておりました。振り降ろされた刀は女に突き刺さり、瞬間、糸が切れたように女の人形が崩れ去ります。後を追うように男は自らの喉に刀を差し、重なるように崩れ落ちました。 「これが事の顛末だ。だが、死んだ場所が悪かったよ。あいつらはあんまりにも奥に行き過ぎたのだ。おかげで見つかりゃあしない。世間じゃ二人がどっかへ逃げたことになっているが……」 黒子のような物の怪は恨めしそうに語りました。そうして近松の顔を覗き込みました。 「どうじゃ?」 物の怪は尋ねました。ですがすぐに答えは出ていると確信し、笑みを浮かべました。というのも、近松の目が作家としての野心を滾らせ、鋭く光っていたからでした。 「お前が脚本(ほん)を書き、義太夫が語ったなら、必ずや黄金の衆は飛びつこう。宇治座との客入り勝負にも勝てようぞ」 物の怪は予言致しました。 「今夜、俺が語った出来事はお前のやり易いよう書き、語るがいい。ただし、これから言う箇所だけは変えるなよ」 そう言って物の怪は男女の人形を担ぐと、襖の向こうに消えていったのでありました。 近松は帰宅をすると、早速執筆に取り掛かりました。 「この世の名残、夜も名残、死に行く道をたとふれば……」 さらさらと筆を進めます。 眠ることも、飯を食らうこともなく、まるで何かに取り憑かれたかのように近松は書き進めました。 物の怪の言う通り、まだ世間に心中の噂は流布しておりません。誰より先に竹本座で取り上げるのだ。その気持ちが筆を押し進めました。 そうして飲まず食わず寝ずの三日三晩でののちに脚本が仕上がりました。近松は義太夫に使いを出すと、憑き物が落ちたような面持ちになって、妻に布団を敷かせると、グーグーと眠り始めました。 「さあ、さあ、寄ってらっしゃい見てらっしゃい! 姥女の奥で男女が情死、心中事件だよ! 男のほうは手代の徳兵衛、女は遊女のお初。そこにお初の身請け話、徳兵衛は借金を踏み倒されたって話だ! 続きは浄瑠璃で見ておくれ! さあ、入った!入った!」 「死にゆく道をたとふれば、あだしが原の道の霜、一足づつに消えていく……」 近松の道行の文句を、義太夫が情感たっぷりに語ります。人形が刀を振り上げ、そして崩れ落ちます。愛を貫くお初と徳兵衛のその姿に人々は熱狂し、芝居小屋は連日押すな押すなの大盛況でした。こうして竹本座と宇治座の勝負は、竹本座に軍配が上がったのであります。 「近松、徳兵衛とお初が見つかったぞ」 興行が始まって三日目の晩、そう言ってあの物の怪が近松の家に現れました。 「あれから姥女森に入ってくもの好きがたくさん出てなぁ。ついに森の奥で二人を見つけたのよ……それともう一つ」 「もう一つ?」 「借金を踏み倒した九平次も捕まった。取調べはこれからだろうが、奴はもう黄金の町では生きていけんだろうなぁ」 物の怪はそう言うと、裂けた口に長い手を入れて、浄瑠璃人形の首をひとつ、取り出しました。そしてごろりと床に転がし、けけけ、と笑いました。 「お前の狙いはそれか」 近松が言います。 「そうとも。俺の力でもって奴を取り殺すことは簡単だった。だがそれではつまらんだろう? そこでお前に頼んだのよ。名前は変えずに、脚本を書いて欲しいとな」 物の怪は満足げにそう答えました。 「お前はなぜそこまでしたのだ? お前は徳兵衛とお初の何だ?」 近松は尋ねました。すると、物の怪その問いを待っていたとでも言いたげに笑ったのでした。 「俺か? 俺はお初の人形よ。尤も、とうの昔に忘れられちまったがなぁ。小さい頃にあんなに遊んでやったのによ」 物の怪は言いました。可愛がられた人形ほど強い呪いを生む、恨人形になるのだと。 「お前さんも浄瑠璃人形を処分するときゃあ、せいぜいこうならぬよう扱うことだ。でなければ、呪いを撒き散らすようになる。俺のようにな」 けけけ、くくくと人形は不気味に笑いました。そうしてこう言ったのでありました。 「いいか近松、これの本質は呪いなのだ」 近松はぞぞっと何かが背を走り抜けるのを感じました。何かとんでもないことをしでかしてしまった気がしたのです。 「呪い? お前の持ち主の復讐ではなかったのか?」 「それもある。だがこれは俺の性質(たち)ってやつなのさ。なぁに今に意味が分かる。今にな……」 そして、人形は近松を称えました。 「お前は大した作家だよ。お前が書き、義太夫が語り、傀儡師が介する。浄瑠璃を通し我が呪いは最高の形になった。世に染みわたったのだ」 そう言い残して、物の怪――恨人形は闇の中に消えてゆきました。 恨人形が語った「呪い」のその意味。それは言葉の通り、しばらく後になって分かりました。 浄瑠璃を通し、男女の心中はたちまち人々を魅了し、世に染みわたったのです。後を追うようにして、様々な芝居小屋が取り上げました。それによりますます多くの人々が事件を知り、酔いしれていったのでありました。そして―― 巷には心中が蔓延るようになりました。若い男女が次々に命を断つ事件があちこちで起きました。姥女森にほど近い黄金の町だけでなく、円寿に、巡り巡って江戸にまで心中の波紋は広がってゆきました。 ――これの本質は呪いなのだ。 恨人形の言葉は現実となったのです。 これを重く見た時の幕府は、とうとう心中ものの上演を禁止する触れを出しました。近松の名を世に知らしめたこの脚本は、時代が変わって支配者が変わるまで、上演されることはありませんでした。 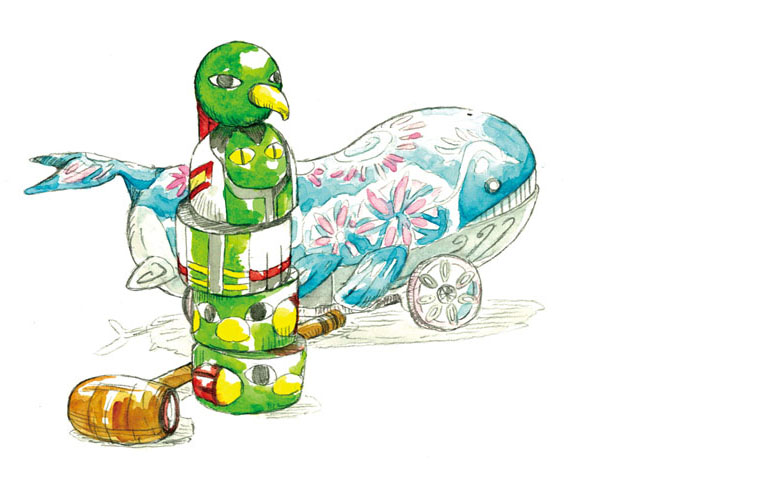 |